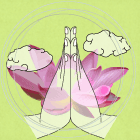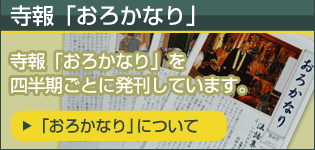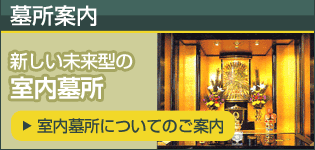第95号「仏教とは」
仏教とは
お釈迦さまの仏教とは、一言でいうと、どんな教えですか?と、尋ねられることがあります。皆さんの中にも、そう思っている方、おられるかもしれませんね。
仏の説かれた教えということですね。今から約二千六百年前にインドで活躍されたお釈迦様のことです。
お釈迦さまはどんな方だったのでしょうか。
《仏教を説かれたお釈迦様》
お釈迦様は約二千六百年前、インドのカビラ城の王様シュッドーダナ王(浄飯王)で、王様の太子として生まれました。 お母さんの名をマーヤー夫人と言い、夫人が出産のため、実家に帰る途中急に産気づきその場で、出産となりました。その場所がルンビニ園という花園だったので四月八日、お釈迦様の誕生日を花祭りといって祝っています。さて、太子が生まれられたときにこんなエピソードが伝えられています。
生まれられたばかりの太子は東西南北に七歩ずつ歩かれそして、天と地を指差されて、天上天下唯我独尊と仰言ったといわれます。有名なお話ですが、皆さんの中にはそんな生まれたばかりの赤子がいきなり立ち上がって歩くはずないだろう、馬の子供じゃないんだから、しかも、しゃべるなんて・・・と思う方もあるでしょう。ですが、このエピソードが意味することは、お釈迦様がこの世に何のためにお出ましになられたかを、私たちに教えてくれているのです。
東西南北に七歩ずつあるかれ、天上天下唯我独尊といわれた、そのこころをお話しましょう!!
「アシダ仙人の涙の訳」
シッダルタ太子の未来を占わせた、浄飯王、ところが、アシダ仙人が太子の顔を見るや否や・・・ハラリ と 涙を流したのでした。驚いた 浄飯王は「太子の顔を見て泣くとどういうわけだ、返事次第では容赦しないぞ!!」と声を荒げます。
アシダ仙人「王様、私は太子の身の上を嘆いて涙したのではありません、自分の不幸を嘆いて泣いたのです」
浄飯王??? それは一体どういうことなのだ・・
アシダ仙人「この太子様、きっと将来、ブッダか 天輪王になられるでしょう。」
ここで、ブッダとは、最高の悟りをひらかれた方、天輪王とは世界を統治する優れた王様、歴史上 世界中を収めた王はいませんが、そういう王様のことを天輪王といわれていました。
当時のインドではまだ最高のさとりをひらいた人は、おりませんでしたが、もし、そのような方が現れたらブッダというと、いうことになっていました。
アシダ仙人「この方がブッダとなられて最高の真理を説かれる頃には、私はもうこの世にはいますまい、こんな尊い方が、この世にあらわれられたのに、さとりの言葉を聞くことが出来ないので私は自分の身の上を嘆いているのでございます。」
すると浄飯王「そういうことなのか ならわかった」と満足したといいます。ですが、浄飯王としては、たった一人の跡取り息子です。当然、立派な王になってもらいたいと思いました。ブッダにするわけにはいかない。何としても立派な王様にしなくては、ここから、浄飯王の太子への英才教育が始まったのです。
シッダルタ太子(のちのお釈迦さま)が深く世の無常を感じ、豪勢な王宮を捨て山で修行されていた時のこと。
一匹のリスが湖水のほとりで尾を水につけては出し、つけては出ししている。不審に思われた太子はリスに尋ねられた。「お前は、何をしているのか」
「私はこの湖水の水をくみ尽くそうと思っています」
リスの言葉に驚かれてシッダルタは
「お前のような小さな尾で一滴二滴くみ出してこんな大きな湖の水をなくすことができると思うのか。何百年かかるか分からぬぞ」と言われると、リスは答えた。
「あなたのおっしゃるとおりでしょう。しかし、私は五年や六年してみて、できなかったと断念するようなことは致しません。どんなに長い年月がかかりましょうとも定めた思いの通るまでは止めない決心をしております」
リスの固い決意に暗示を得られたシッダルタ太子は「自分も今、このリスに勝っても劣らぬ大願をおこしているのだ。たとえ何十年かかろうが、最初の目的を果たすまでは志を曲げてはならないぞ」と修行を続行し、ついに仏の覚りを成就せられたのです。
中国の儒教で有名な白楽天(はくらくてん)も、そんな疑問を抱いていたようです。昔、中国に、いつも樹の上で、坐禅瞑想していた 「鳥窠(チョウカ)」 という僧侶がいました。ある日、白楽天が、その樹の下を通って、瞑想をしている樹上の僧侶を冷やかしてやろうと思ったのです。「そこの坊さん、そんな高い木の上で目をつむっていては、危ないではないか」鳥窠は、すかさず、「そういう貴殿こそ、危ないぞ」と切り返しました。この坊主、相当の奴かもしれぬと見てとった白楽天は、「私は、名もなき白楽天という儒者だが、貴僧のご芳名を承りたい」と聞くと、「私は、名もなき鳥窠という坊主だ」鳥窠と聞いて、白楽天は驚いた。これが いま高名な、鳥窠禅師かと知った白楽天は、かねてから仏教に関心を持っていたので、こう言って頭を下げた。「いいところで、貴僧に会った。一体、仏教とはどんな教えか、一言でご教授 願いたい」即座に、鳥窠禅師は答えています。「もろもろの悪を為すことなかれ、つつしんで善を修めよ、と教えるのが仏教である」(どんなことであれ悪いことはしてはならない。できる限り善いことをしなければいけない。そうすればおのずから心は浄くなる。これが仏教の教えだ)と答えられた。白楽天は「そんなことだったら、小さな子供でも知っていることでしょう」と詰(なじ)ると、「三歳の子供でも知っていることを、八十の老人でさえ行なうことが難しいのだ」と言われた。
綺麗な廊下に紙屑が落ちていたとしよう。どんな人でもそれを見れば、拾ってゴミ箱にいれようかという気持ちが起こるものです。人間というものには生まれつき、仏のような素晴らしい心が具(そな)わっているからです。ところがすぐ後から、「自分がしなくても、誰かがするだろう」という悪魔の声がして、せっかくの仏心が踏みにじられてしまうのです。だからわれわれはそういう悪心に負けないように、最初起こった気持ちのままに行動すればいいのだ。そう言われても、何となく気恥ずかしいまま通り過ごしてしまうのが、人情というものかも知れないです。又、電車に乗って、ようやくの思いで空席を見つけ、ホッとして坐っていると、次の駅で老人が乗ってきて傍に立った。代わってあげるべきだという気持ちは、どんな人にでも具わっている。だから立たないで居眠りの振りをするのは心苦しい。にもかかわらずすっと素直に立てないというのは、何という悲しい人間の性であろうか。そういいながら実践不履行のままでは、自分が仏教徒であるということさえ憚(はばか)られるのではないか。知っていても、実行しなければ、知らないのと同じだからです。仏教を一貫して教えは、因果の道理(いんが の どうり)です。「善因善果 悪因悪果 自因自果」は、三世十方を貫(つらぬ)く、いつでも どこでも 変わらない真理です。
「善因善果」とは、善い因(行為)は、善い果(幸福や楽しみ)を生み出す。
「悪因悪果」とは、悪い因(行為)は、悪い果(不幸や苦しみ)を引き起こす。
「自因自果」とは、自分に現れる善果も悪果も、すべて自分のまいた因(行為)によるものだから、自分が刈り取らなければならない、ということです。
この真理に立てば、「悪いことをやめて、善をせよ」の「廃悪修善」になるのは 当然ですね。
つまり、お釈迦さまの教えは、「あなたに現れる、不幸や災難は、あなたの蒔(ま)いた、悪い因が生み出したものなのですよ(悪因悪果・自因自果)。不幸になりたくなければ、悪い行いを慎みなさい」の「廃悪」の教えになりますね。
そしてまた、お釈迦さまの教えは、「あなたの幸福は、あなたの蒔いた善い因が生み出すものなのだから(善因善果・自因自果)、幸せになりたければ、善い行いをしなさい」の「修善」の勧めになります。誰もが、「不幸」を厭い「幸福」を求めて生きているのですから、仏教は、すべての人に「廃悪修善」を勧められている、ということです 。では、どんなことが「善」で、どんな行為が「悪」なのでしょう? 「十善(じゅうぜん)」「十悪(じゅうあく)」など、 お釈迦さまは 教えられていますので、まず 教えを よく聞くことが 大切です!
十善戒 じゅうぜんかい
十項目からなる善の戒めを十善戒と言います。戒めですから自発的なものです。特に十善戒は、生き方、人としての道、を示したようなものです。
不殺生(ふせっしょう) あらゆる生命を尊重しよう
不偸盗(ふちゅうとう) 他人のものを尊重しよう
「偸盗」すなわち他人の財産を盗むことは、殺生・ 邪淫とともに人間の身に備わった根本的悪業の一つ に数えられます。仏教においては道徳を越えて、貪 欲(とんよく)や瞋恚(しんに)という真実に対する 叛逆の結果としての「盗み」を糾(ただ)すのです。 不邪淫(ふじゃいん) お互いを尊敬しよう
「邪淫」とは、夫婦以外の者と肉体関係を持つこと、 もしくはそれに至るおそれがあるような行為全般を 指します。仏教では、性欲に支配されることは貪欲 (とんよく)瞋恚(しんに)愚痴(ぐち)といわれる 「三毒の煩悩」の中、正しいものの見方を妨げる、 もっとも強大な煩悩であると考えました。
不妄語(ふもうご):正直に話そう
人間における言語の使用は、仏智・神智ヘの叛逆と いう結果となって、対立・混乱の世相を助長してき たのです。五戒では、悪口(汚い言葉)両舌(二枚舌)、 妄語(うそをつくこと)綺語(おべんちゃら)のすべ てを「妄語」取り込んで、これを戒めるのです。
不綺語(ふきご) よく考え話しましょう
綺語(きご)というのは、言葉をうまくあやつり飾 ることです。「お世辞やへつらいを口にしません」
結局偽りを言っていることなんですよね。心にもな いお世辞やへつらい言葉を口にすること。「あ~ら、 奥様!いつもお若くてお美しくあられて~・・・。」 という言葉の裏には、『あ~ら、ずいぶんとお化粧 品代つぎ込んでるのネ~』という本心が。まあ、い ろんな人とお付き合いする中では、少々見え透いた お世辞など口にした方が、巧く事が運ぶと考えるか も知れませんが、これは大きな勘違いです。実は、 その綺語を何となく心地よく受け入れて、驕り高ぶ らせるのも大きな災いの要因になります。言う方も 言われる方も罪を生み出しているのです。口にする 言葉は真実であるべきです。どうしても真実を言え ない、または言わない方が良い場合は、口を開くな!
不悪口(ふあっく) 優しいことばを使おう
不両舌(ふりょうぜつ) 思いやりの言葉を話そう
不慳貪(ふけんどん) 惜しみなく施しをしよう
不瞋恚(ふしんい) にこやかに暮らそう
不邪見(ふじゃけん)です。正しく判断しよう
いずれも最初に不が付いているので、つづく二文字のことをしない、と言うことになります。十善戒は悪をやめ、善を行わせる戒です。
十悪 じゅうあく
十善戒のから不を取ったものが十悪です。人の行為から三種類に分類できます。
■身による悪
殺生 生きものの生命を奪う。
偸盗 与えられていない他人の財物を取る=盗み。
邪婬 よこしまな男女の交わり。
■口による悪
妄語 嘘をつく。でたらめを言う。
綺語 無意味、無益なことを言う。
悪口 他人を傷つける言葉。陰口、中傷。
両舌 他人の仲を裂く言葉。
■意(心)による悪
慳貪 財物などをむさぼり求める。異常な欲。
瞋恚 いかり憎む。
邪見 誤った見解。
分類と項目数を合せて、身三口四意三(しんさんくしいさん)という呼び方があります。口に関することが四つで、他より多いのは、それだけ言葉遣いは難しいということです。 終わり