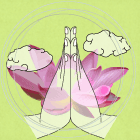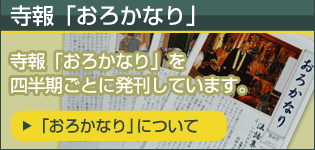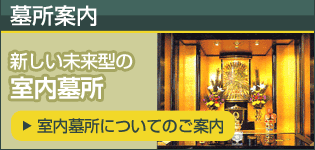葬儀を終えて
今一度、葬儀について考えてみたいと思います。中二のご子息を亡くしたお母さんは、こうおっしゃています。「法要も読経も合掌して念仏称えるのも、亡くなった息子のためという考え方は、とんでもない見当違いでした。仏になった息子から頂くばかりの私だったと気付かされ、(息子にありがとう)と手を合わさずにはおられません。住職さんが(息子は人生の先生です。恩師です)といわれたのが、はっきりわかりました」この言葉から、次のことが教えられます。
1.読経や合掌は亡くなった人のためで はない。
2.仏さまに手を合わす心。
3.住職の仏道への確かな導き。
葬儀でよく耳にする「ご冥福をお祈りします」「安らかにお眠り下さい」は、まさに亡き人のための手の合わせ方なのでしょう。お母さんは,慰霊の寺参りを欠かさなかったといいますから、死後の間違いのない幸福を祈ったに違いありません。自らの力ではどうすることもできないお母さんは、悩み・苦しみ、何度も自殺を考えたそうです。ところが、浄土真宗の教えを聞き、住職と言葉を交わすうち、何がなんでも自分の思いどおりに運ばせたいという自我の執着にどっぷりつかっていた自分がわかってきたといいます。浄土真宗の教えの言葉が亡き息子からの無言の呼びかけとして、聞こえてきたのでありましょう。お母さんは息子から、人間としての生き方を教えられ続けていたのです。それが、「息子から頂くばかりのわたしだった」という気づきではないでしょうか。ここに、亡くなった息子を仏さまと仰ぎ、合掌せずにはいられない心が生まれてきたのでしょう。通夜・葬儀は、慌ただしく始まり、慌ただしく終わります。だからといって、単なる一過性のものではありません。残された人生を仏さまから、そして亡き人から聞きたずねる大切な時間なのです。葬儀を終えた後も、住職の法話を大切にされ、自らの確かな人生を学び歩んでいただきたいと思います。